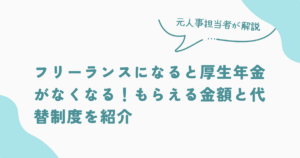「フリーランスの厚生年年金はどうなるの?」
「会社を辞めたら入れないって聞いたけど、本当かな…」
「もらえる額は減らしたくないな」
フリーランスを目指す方は、このような悩みをお持ちではないでしょうか。
特に、厚生年金への加入や将来もらえる年金額について疑問や不安を感じる方は少なくありません。
会社員とは異なり、フリーランスは原則として厚生年金に加入できず、将来受給できるのは国民年金(老齢基礎年金)のみとなります。
 まつお
まつおそのため、年金の仕組みについて理解し、将来に向けた準備を進めることが重要です。
この記事では、フリーランスと会社員の違いや年金の仕組み、受給額の目安などについて解説します。
さらに、厚生年金の代わりとして活用できる制度や節税方法についても紹介するので参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 年金の基礎知識
- 年金はいくらもらえるのか
- 年金の支払いが難しい場合の対処法
- 厚生年金の代替制度
- 保険料の節税対策
フリーランスの方やこれから独立を考えている方の一助となれば幸いです。
フリーランスが知っておくべき年金の基礎知識
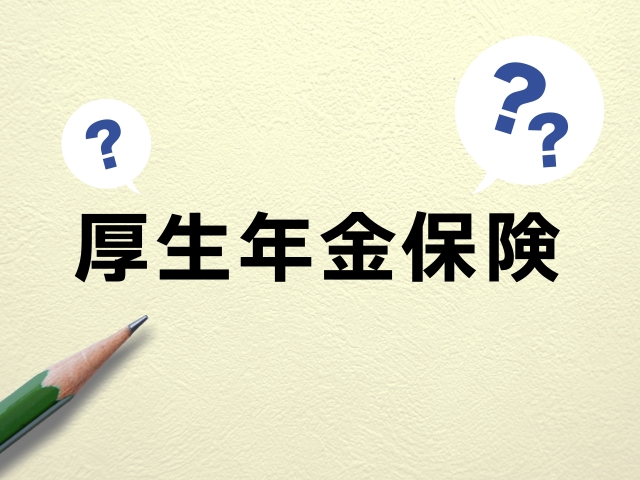
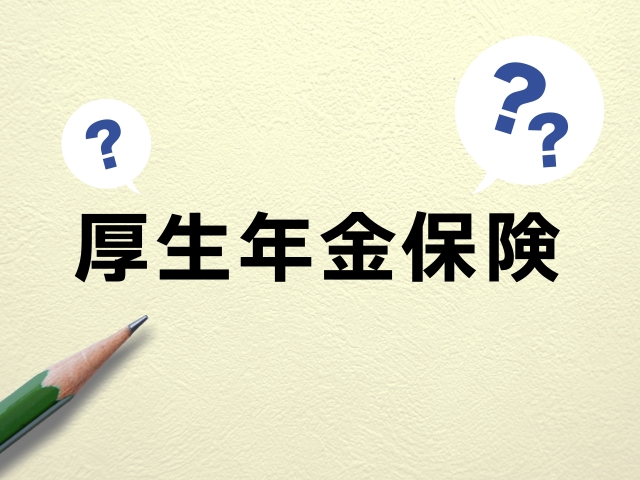
フリーランスとして働く方にとって、年金制度を理解することは将来設計をする上でとても重要です。
まずは、どのような仕組みになっているのか把握しておきましょう。
- 国民年金の仕組み
- 厚生年金の仕組み
- 年金は二階建て構造になっている
それぞれ詳しく解説します。
国民年金の仕組み
国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。自分で保険料を納める必要があります。
会社員は自分の代わりに企業が保険料を建て替えて払ってくれてますが、独立したら自分で国民年金への加入手続きをしなければなりません。



保険料を納めることで、65歳から「老齢基礎年金」を受け取れます。
ただし、満額の年金を受け取るためには、20歳から60歳までの40年間すべての期間保険料を納めることが条件です。
保険料の未納期間があると、その分だけ将来の年金受給額が減少してしまいます。
未納期間を作らないためにも、会社を辞めたらすぐに手続しましょう。
厚生年金の仕組み
厚生年金は、会社員や公務員などが加入する制度です。
厚生年金の保険料は給料に応じて決まり、保険料の半分は会社が負担してくれます。
フリーランスは厚生年金に加入できず、保険料は全額個人負担です。
ただし、フリーランスでも、法人を設立すれば厚生年金への加入ができます。
厚生年金に加入していると、老齢基礎年金に加えて「老齢厚生年金」も受け取れるため、受給額が大きく増えるのがメリットです。
そのため、売上を大きくして法人化するフリーランスの方も少なくありません。
年金は二階建て構造になっている
年金制度は「二階建て構造」の仕組みになっています。
二階建てとは、全国民が加入する「国民年金」を一階部分とし、会社員や公務員などが上乗せで加入する「厚生年金」を二階部分とするという意味です。
フリーランスの方は一階部分の国民年金のみに加入となり、二階部分の厚生年金には加入できません。
そのため、会社勤めをやめてフリーランスになった場合は、これまで加入していた厚生年金を脱退する必要があります。



脱退の手続きは、会社がやってくれるので心配ありません。
フリーランスの年金はいくらもらえる?


フリーランスが将来受け取れる年金額は多くの方が気になるポイントです。
会社員と比較してどのくらいの差があるのか、老後の生活に十分な金額であるかの把握が欠かせません。
以下の3つを押さえておきましょう。
- 年金の受給資格
- 受け取れる年金の種類
- 受け取れる金額
これらについて詳しく解説していきます。
年金の受給資格
まず知っておきたいのが「年金を受け取るための条件」についてです。



年金を受給するには、一定の加入期間を満たす必要があります。
国民年金は、20歳から60歳までの40年間が加入期間です。この期間の保険料を全て納めると、65歳から老齢基礎年金を満額でもらえます。
ただし、10年以上納めていれば、納付した期間に応じた金額の受給が可能です。
学生などで収入がない場合は、保険料免除や納付猶予の手続きをしておけば、将来の年金受給権を確保できます。
免除や猶予の措置を受けた期間は未納の扱いにはなりませんが、満額は受け取れないため注意が必要です。
受け取れる年金の種類
年金として受け取れるものには、老齢基礎年金以外にも複数の種類があります。
主な年金の種類としては、以下の3つです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | ・65歳から受け取れる基本的な年金 ・保険料の納付期間に応じて受給額が決まる |
| 障害基礎年金 | ・病気やケガで障害を負った場合に受け取れる ・年金障害の程度に応じて1級と2級がある |
| 遺族基礎年金 | 加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、その遺族に支給される年金 |



これらの年金は、国民年金に加入していれば受給の対象となります。
「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」は、万が一の際の備えになるでしょう。
ただし、保険料の未納期間がある場合は受給できない可能性があるため、保険料の納付は欠かせません。
国民年金はいくら受け取れる?
フリーランスが老後に受け取れる老齢基礎年金の金額は、保険料の納付期間によって決まります。
2024年度の老齢基礎年金の満額は、年間81万6,000円(月額6万8,000円)です。



満額を受け取るためには、20歳から60歳までの40年間すべての期間の保険料を納めなければなりません。
もし、保険料の納付期間が40年に満たない場合は、以下の計算式で年金額が算出されます。
年金額 = 82万円(満額)× 保険料納付月数 ÷ 480ヶ月
例えば、30年間(360ヶ月)納付した場合を見てみましょう。
82万円 × 360 ÷ 480 = 61万5,000円(月額に換算すると、5万1,250円)
免除を受けた期間がある場合は、免除の種類に応じて一定割合が年金額に反映されます。
このように、フリーランスが受け取れる国民年金は月額5万円程度であり、これだけで老後の生活を賄うのは難しく、追加の年金対策が欠かせません。
フリーランスになって年金の支払いが難しくなったら


フリーランスとして働いていると、収入が不安定で国民年金の保険料の支払いが難しくなる時期があるかもしれません。
しかし、保険料を未納のままにしてしまうと、将来の年金受給額が減ります。
そのような状況に備え、以下の2つの救済制度が用意されているので覚えておきましょう。
- 保険料免除制度
- 保険料納付猶予制度
それぞれについて詳しく説明します。
保険料免除制度を利用する
保険料免除制度とは、収入が少ない場合や災害で被害を受けた場合などに、国民年金の保険料の支払いを免除してもらえる制度です。
免除には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があり、所得に応じて適用される免除の割合が決まります。



例えば、単身者の場合、全額免除の目安は年間所得が67万円以下です。
申請は住んでいる市区町村の役所で行い、認められると免除期間も受給資格期間にカウントされます。
ただし、全額免除の場合、将来の年金額は保険料を納めた場合の2分の1として計算されるため注意が必要です。
一部免除の場合は、減額された保険料を納付すれば、その期間に応じた年金額を確保できます。
また、免除を受けた期間は、10年以内であれば後から保険料を納めることも可能です。
追納すると、その期間は満額の年金を受け取れる期間として扱われます。
保険料納付猶予制度を利用する
保険料納付猶予制度は、50歳未満で収入が少ない場合に利用できる制度で、本人の所得が一定基準以下の場合に申請が可能です。
納付猶予が認められると保険料の支払いが一時的に猶予され、その期間も受給資格期間にカウントされます。
保険料免除制度との違いは、納付猶予は将来の年金額の計算には含まれない点です。
ただし、10年以内であれば、追納することで年金額に反映されます。
そのため、収入が回復したらできるだけ早い段階での追納しましょう。
フリーランス向けの厚生年金の代わりとなる老後年金対策


フリーランスは厚生年金に加入できないため、国民年金だけでは老後の生活資金が不足する可能性があります。
会社員の場合、厚生年金を合わせると月に約13〜15万円受け取れるのに対し、フリーランスは月に6万8,000円しか受け取れません。
そこで、以下のような方法で、国民年金だけでは足らない老後資金を準備する必要があります。
- 国民年金基金
- 付加年金
- iDeCo
- 小規模企業共済
- 個人年金保険
これらについて、見ていきましょう。
国民年金基金
国民年金基金は、国民年金に上乗せする形で受給できる制度です。国民年金の加入者であれば誰でも加入できます。
特徴は、加入時に選択した掛け金と受取額が約束されている「確定給付型」であることです。
一度決めた掛け金は原則として変更できませんが、老後の受取額が確実に保証されるため安心感があります。
受取開始年齢は65歳からで、2種類の終身年金または5種類の確定年金から選択が可能です。



掛け金は、月額5,000円から6万8,000円の範囲で決められます。
ただし、掛け金と受取額は加入年齢によって変わるため、早めに加入するほど有利です。
詳しくは厚生労働省が発行しているパンフレット「国民年金基金のご案内」をご覧ください。
付加年金
付加年金は、国民年金に少額を上乗せ納付して老後の年金額を増やせる制度です。
国民年金の定額保険料(月額1万7,510円)に加えて、月額400円を追加して納めます。
400円を納めれば、年額で「200円×付加保険料納付月数」を追加で受け取ることが可能です。



例えば、40年間(480ヶ月)付加年金を納めると…
年間9万6,000円の追加年金を受け取れます。
付加保険料の総額は40年間で19万2,000円なので、約2年で元を取れる計算になり非常に効率の良い制度といえるでしょう。
国民年金保険料を納めている方であれば誰でも申し込めます。
ただし、iDeCoと付加年金は同時に加入できないため注意が必要です。
iDeco(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で掛け金と運用方法を決めて老後資金を準備する制度で、毎月最大68,000円まで掛け金を拠出できます。
以下の、トリプルの税制メリットを受けられるのが特徴です。
- 掛け金が全額所得控除になる
- 運用益が非課税
- 受け取る際の税制優遇
商品も元本確保型の定期預金から、国内外の株式や債券に投資する投資信託まで、自分のリスク許容度に合わせて投資対象を選べます。
長期間の運用による複利効果も期待できるため、早めに始めるほど資産形成がしやすい点がメリットです。



ただし、以下の点には注意する必要があります。
- 原則として60歳まで引き出せない
- 運用次第では元本割れするリスクがある
- 毎月の管理手数料がかかる
加入手続きは、金融機関や証券会社で行なってください。
小規模企業共済
小規模企業共済は、事業主やフリーランスのための「退職金制度」のようなものです。
月額1,000円から70,000円までの範囲で積み立て、廃業時や65歳以上で解約する際に退職金として受け取れます。
この制度の特徴は、65歳以上での解約や廃業による解約の場合は「退職所得」として税金が優遇される点です。



ただし、それ以外の理由での解約は「一時所得」となり、税制上の優遇度が下がります。
加入条件は、「事業所得のある個人事業主」「保険業などを除く法人の役員」などとなっており、フリーランスでも収入を事業所得として確定申告していれば加入できます。
中小機構や金融機関で手続きが可能です。
個人年金保険
個人年金保険は、民間の保険会社による老後資金準備のための金融商品です。
毎月一定額を保険会社に支払い、年金形式で受け取る仕組みとなっています。
商品によって終身型や確定型などがあり、死亡保障が付いているものや、医療保障が組み込まれているものなど選択肢が豊富です。
税制面では、支払った保険料の一部が「個人年金保険料控除」として、年間最大6万8,000円まで所得控除の対象となります。
個人年金保険のメリットは、商品選びの自由度が高く、自分に合わせた保障内容や受取方法を選べる点です。
一方、解約返戻金が元本を下回るリスクや、手数料がかかることは考慮しておく必要があります。
フリーランスが年金の保険料を節税する方法


フリーランスにとって、税金対策は収入を増やすのと同じくらい重要です。
特に、年金保険料は適切に納付することで節税にもつながり、将来の年金受給額も確保できる一石二鳥の対策となります。
ここでは、フリーランスが年金保険料を効果的に節税できる3つの方法を見ていきましょう。
- 国民年金保険料を2年分まとめて払う
- 家族分の国民年金保険料もまとめて払う
- iDeCoを利用する
それぞれ詳しく解説します。
国民年金保険料を2年分まとめて払う
通常、国民年金の保険料は毎月納付ですが、6ヶ月、1年、2年とまとめて前納すると割引が適用されます。
特に2年分をまとめて前納すると、1万5,670円の割引となりお得です。
支払った保険料全額が社会保険料控除の対象となるため、節税効果も得られます。
例えば、所得税率20%の場合、年間の国民年金保険料約20万円を納めると約4万円の軽減です。
2年分をまとめて納めると、その年の社会保険料控除が増えるため、一時的に大きな節税効果を得られます。



年度の途中からでも、翌年度以降の分をまとめて納めることが可能です。
家族分の国民年金保険料もまとめて払う
家族の保険料を自分が支払うと、全額が支払った本人の社会保険料控除として申告できます。
誰が保険料を支払ったかが重要であり、実際の被保険者が誰であるかは関係ありません。
例えば、フリーランスの方と専業主婦の配偶者がいる場合、配偶者の国民年金保険料も自分が支払うことで、その分の社会保険料控除を受けられます。
年間で約20万円の追加控除となり、所得税率20%の場合、約4万円の節税効果があるのです。



ただし、控除を受けるには自分が支払った事実を証明する必要があります。
家族分の国民年金保険料を支払ったことを証明する納付書や、領収書を保管しておきましょう。
iDeCoを利用する
iDeCoは、老後資金準備と節税を同時にできるメリットがあります。
最大の特徴は、月額最大68,000円まで拠出でき、その全額が所得から控除される点です。
例えば、年間60万円をiDeCoに拠出した場合、所得税率20%、住民税率10%と仮定すると、年間18万円(60万円×30%)の税金が軽減されます。



これは実質的に国から30%の上乗せがあるのと同じです。
さらに、運用益は非課税で、受け取る際にも税制優遇があります。
リスク許容度に応じて元本確保型の預金から株式投資まで幅広い選択肢があるため、金融機関やFPなどに相談すると良いでしょう。
フリーランスは自分で老後資金を確保する必要がある


フリーランスは原則として厚生年金に加入できず、国民年金のみとなります。
会社員と比較して、将来受け取れる年金の受給額が少なくなるため、自分で老後資金を準備しなければなりません。
本記事で紹介した国民年金基金やiDeCo、小規模企業共済といった制度を利用して年金を積み増すことが重要です。
これらの制度は、老後の所得保障を手厚くするだけでなく、掛金の所得控除による節税メリットも得られます。
フリーランスの老後資金問題は自分で考えて対策が必要です。
将来の生活を安心して迎えるためにも、早い段階から年金制度の仕組みを理解し、自分に合った備えをしましょう。